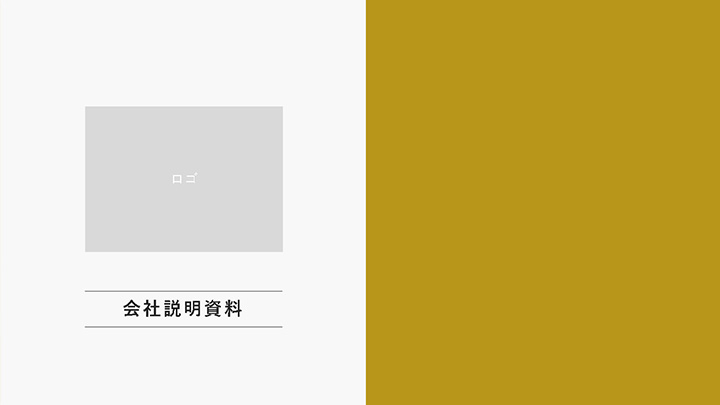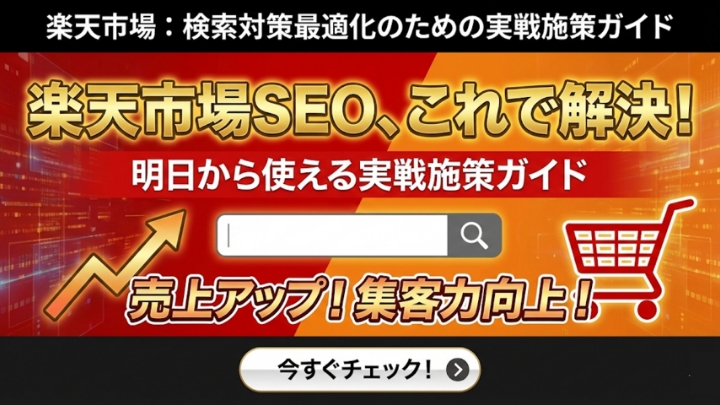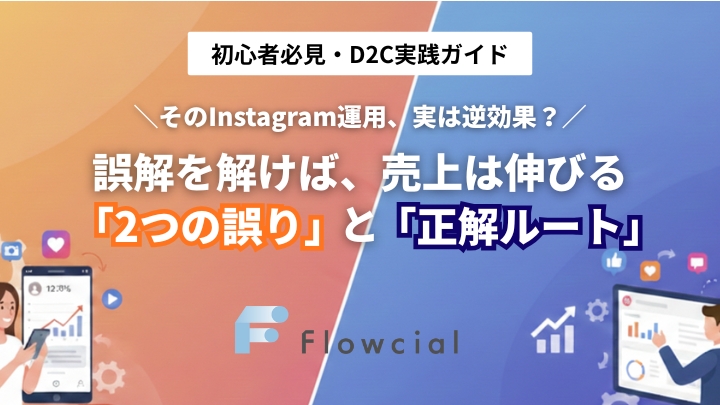いつも見て頂きありがとうございます!「エンプレス」の編集部:sugiyamaです。ビジネスの中に、どんどんAIが入り込んできて、目まぐるしく状況が変わり、webに対する対策が追いつかない方は、ぜひ見てほしいです!
生成AIの波によって、webの「当たり前」が変わりました。
Googleで調べ物をすると、画面の一番上にAIのまとめた答えがドンと表示され、わざわざ元のサイトを見に行かない…そんな経験していますよね。
ChatGPTやGeminiのような「AIから直接回答をもらう」「AIに直接質問する」のが当たり前になりつつあります。
こんな時代に「うちの会社のwebサイト、どうしたらお客様に見てもらえるんだろう…」と不安にも感じませんか?
これまでの王道はSEO(検索エンジン最適化)でしたが、この手法も通用しないんじゃないかとモヤモヤしているかもしれません。
実はAI時代の新しい波へ対応するためLLMO対策(Large Language Model Optimization:大規模言語モデル最適化の略)がバズワードとなっているのですが、LLMO対策は多くの人が誤解していることが多く、表面的なテクニックの話だと思われがちですが、本当はもっとずっと深く、そして企業の未来を左右するほど大切な「覚悟」の話なんです。
この記事では、AI時代に企業が生き残り成長していくために、LLMO対策の本質が何なのかを、とことん分かりやすく解説していくので、小手先のテクニックに踊らされることなく、本質的なコンテンツ作りに役立つ情報となれば幸いです。
- 目次
- LLMO対策って結局何?その目的と従来のSEOとの決定的な違い
- LLM時代に低価格コンテンツが「企業の没落」を招く理由
- LLM時代に選ばれるためのコンテンツの「本質」と「具体的要素」
- LLM時代における企業に問われた覚悟
- LLMO対策のその先へ:見込み顧客の獲得とブランド形成
- LLM時代は「本物」だけが生き残り未来を創る
LLMO対策って結局何?その目的と従来のSEOとの決定的な違い
「LLMO(エル・エル・エム・オー)対策」
この言葉は聞き慣れないかもしれませんね。
まずはその意味と、今まであなたが取り組んできた「SEO」と何が違うのかを、ハッキリさせていきます。
LLM時代におけるコンテンツの新しい役割
AIがどんどん賢くなり、私たちは日常的な情報探しの手段を変えられました。
以前は何かを知りたいとき、Googleの検索ブラウザへ「〇〇 おすすめ」「△△ やり方」などのキーワードを打ち込めば、たくさんwebサイトのリストを見せてくれて、その中から「これだ!」と思うサイトを選んでクリックしていましたよね。
この「リストの上位に表示させる」ための工夫が、これまでのSEO(検索エンジン最適化)で、主流のデジタルマーケティングでした。
しかし、今はGoogleの検索結果画面の一番上には、AIがまとめた「AIによる概要」が表示されるようになり、もっと踏み込んでChatGPTやGeminiのようなAIに直接質問することも日常的になりました。
つまり、AIが私たちの質問に「直接答えてくれる」ようになったのです。
これが何を意味するかといえば、ユーザーはもはや、わざわざ検索結果からサイトを選び、クリックして、そのサイトの中を読み込みに行く手間をかけなくなっていること。
AIが賢く回答してくれるので、引用元(つまりあなたのwebサイト)すら見られないのが「普通」になりつつあります。
この状況で、あなたのwebサイトのコンテンツを「見つけてもらう」ために、まずはAIから「これはぜひ使うべき情報だ!」と選ばれる必要があります。
コンテンツの役割は、単に情報を提供することから、AIとユーザーに「信頼される情報源」となり、「ブランド」として認識されることへと大きく変わってきているのです。
LLMO対策の究極の目的
LLMO対策と聞けば、新しいテクニックの話に聞こえるかもしれませんが、その究極の目的は会社にとって昔から変わらない、非常にシンプルで大切なことです。
それは「会社のお客様を増やしビジネスを成長させる」こと。
もう少し具体的に言うと、以下の3つがLLMO対策のゴールとなります。
ゴール① 質の高い見込み顧客を引き寄せ顧客へ変えること
AIによる一次回答は今すぐ知りたい情報が簡単に分かるので、もう一段先の深い悩みや具体的なニーズが発現するフェーズへ移行しやすくなります。
そのためAI回答を通じて見込みの高い方にコンテンツを見に来てもらい、最終的には自社の顧客となってもらうことを目指します。
ゴール② 会社のブランド価値を高め信頼されること
あなたの会社のコンテンツがAIに選ばれ、多くの人にとって「ここが一番詳しい」「この会社の情報が一番信頼できる」と思ってもらえるようになれば、それは会社にとって強いブランドになるキッカケとなります。
ブランドが強くなるほど、自然とお客様が集まってくるだけでなく、ビジネスの信頼性も高まります。
ゴール③ 会社の成長と他社に負けない強さを手に入れること
競合他社がただ量産型のコンテンツを作っている中で、自社が「本物の情報」を提供できれば、それは他社には真似できない、圧倒的な競争力になります。
ゴール①と②の取り組みを通じて、会社は安定的に成長を目指せます。
従来のSEO対策とLLMO対策の決定的な違い
従来のSEO対策と現代のLLMO対策は、何が違うのでしょうか?
同じように思われがちですが、それぞれ根本的な「目的」と「アプローチ」に違いがあります。
従来のSEO(検索エンジン最適化)の考え方
| 目的 | Googleなどの検索エンジンに、自社のwebサイトを見つけてもらい、特定のキーワードで検索結果の上位に表示させることが主な目的でした。 |
|---|---|
| 対象 | 主に検索エンジンのアルゴリズム(ロボット)を意識していました。 |
| 対策 | ・webサイトの技術的な改善(表示速度、モバイル対応など) ・キーワードを記事内へ適切に配置する ・他のサイトからのリンクを増やす(被リンク対策) ・検索エンジンの評価基準(ランキング要因)に合わせて、webサイトやコンテンツを最適化する「手段」が主軸でした |
LLMO対策(大規模言語モデル最適化)の新しい考え方
| 目的 | 生成AI(GoogleのAI概要やChatGPTなどの対話型AI)に、自社のコンテンツを「最も信頼でき、価値がある情報として引用したい」「ユーザーへの直接回答の根拠にしたい」と思わせること。そのコンテンツを通じて、ユーザーとの「信頼関係を築き、最終的に顧客にする」ことが目的です。 |
|---|---|
| 対象 | 生成AI(より複雑な思考プロセスを持つAI)、そしてその先にいる人間のユーザー、双方を意識します。 |
| 対策 | ・「最高品質のコンテンツ」を創造し、AIが理解しやすいだけでなく、人間のユーザーが心から満足する情報を提供すること ・単なるキーワードの最適化ではなく、ユーザーの深い検索意図を理解し、その意図を完全に満たす「究極の価値」を提供すること ・コンテンツそのものが持つ「専門性」「信頼性」「独自性」「権威性」といった本質的な要素を徹底的に高めること ・最終的には、「選ばれる」「信頼される」ための戦略、つまり自社のブランドそのものを構築することが主軸となる |
違いを理解することでLLMO対策ができるようになる
従来のSEOが主に「見つけてもらう」ための「手段」に焦点を当てていたのに対し、LLMO対策は「選ばれる」「信頼される」ための「戦略」であり、より本質的な価値とブランドの構築に重きを置いている点で大きく違ってきます。
もはやキーワードの対策数を増やしたり、小手先のテクニックでは通用しない時代に突入しています。
LLM時代に低価格コンテンツが「企業の没落」を招く理由
これまでの話からLLMO対策が、小手先のテクニックではなく、会社の未来を左右する大切な覚悟の話であることは、なんとなくイメージできましたでしょうか。
では、なぜそうまでして「覚悟」が必要なのか。
それは、これまで多くの企業が陥りがちだった「安さ重視の量産型コンテンツ」が、今や会社にとって費用対効果に見合わない「マイナス投資」になりかねない状況だからです。
AIによる均質化とコンテンツ飽和の現実
「AIを使えば、記事なんてあっという間に作れるんでしょ?」と、このようなお声はよく聞きます。
確かに、生成AIの技術力だけを見れば、一般的なブログ記事を1時間に何本も「生成する」ことは、物理的には可能。
例えばある会社がAIを活用した場合
1時間で2,000文字程度の記事を5本
1日(8時間稼働)で40本
1ヶ月(20日稼働)で800本
このくらい大量の記事を「生成」し、webサイトに投稿できる可能性もあり、数字だけ見るとかなりの効率性です。
しかし、この「量産」は自社だけでなく、競合他社も、そして個人ブロガーでさえ、これと同じか、それ以上の速度で記事を「生成」できる現実を忘れてはいけません。
インターネット上は、AIが作った「そこそこの記事」で溢れかえっています。
仮に1時間で5記事を生成しても、インターネット上には、AIが作った類似記事がその何十倍、何百倍もの速さで毎時間生まれている。
Googleや他のAIはもう低品質な「数」に見向きもしません
AIが回答を直接提供するようになった今、GoogleのAI(AI概要など)がユーザーに提示するのは、本当に厳選された現時点の最高品質の情報の『上澄み』だけ。
安価にパッと作った記事は、その上澄みには決して含まれず、たとえそこそこの品質だったとしても、AIはより信頼性が高く、より深い情報源を優先します。
そのため今後、AIが引用しない記事は、存在しないのと同じことにもなりかねない。
もしあなたの記事がAIの学習対象になったとしても、それがAI回答の「元ネタ」として選ばれなければ、ユーザーの目に触れることはありません。
結果として、永久に誰にも見つけられない情報にもなってしまいます。
このように「自社ができるなら、他社も同じようにできる」。
そして同じことを効率的にやったところで、情報爆発時代の中では誰にも見つけてもらえないのは当然と言えます。
「安さ」への固執がもたらす致命的な損失
「安ければたくさん記事が作れるから、会社のwebサイトのコンテンツが増えて、社内評価も上がるはずだ」と考えている企業も少なくないかもしれません。
しかし、この安さ重視の考え方が、実は将来的な利益を失う、致命的な要因になる可能性が高くなるのです。
今までの安さ戦略に固執することは、一時的なコスト削減に見えて、実際には企業の集客不足を招く無意味な投資となりつつあります。
安い制作費用は消えてなくなるコスト
たとえ1記事あたりの制作単価が安くても、それが誰にも見られず、誰の役にも立たないのであれば、その費用は回収されるどころか、ただ消えてなくなるだけ。
年間で数百万円、数千万円を投じても、それが「見られない記事」に費やされているとしたら、これほど無駄な投資はありません。
安さはブランド力と信頼性の低下を招く
質の低い、どこかで見たようなコンテンツは、単に見られないだけでは済みません。
もし仮に一部の目に触れたとしても、その薄っぺらい内容や、インターネット上の情報を適当にまとめただけの記事では、専門性や信頼性を損なうことにつながります。
「この会社が発信する情報は、質が低いな」「どこかの真似事ばかりだな」と一度思われたら、お客様は二度と信頼しなくなる可能性も。
これは、会社にとって非常に大切なブランドイメージを自ら傷つけてしまう行為でもあります。
安さは未来への機会損失という見えないコスト
費用をかけるのであれば、未来の顧客を呼び込み、会社のブランドを構築する、質の高いコンテンツに投資したほうがいいと考えています。
しかし、低品質な記事に投じるコストは、将来的な本当の意味での投資の機会を奪っていることに他なりません。
LLM時代を生き抜くために必要なコンテンツへの覚悟を育む機会を、自ら手放しているとも言えます。
LLM時代に選ばれるためのコンテンツの「本質」と「具体的要素」
LLM時代に選ばれるコンテンツとは、一体どのようなものなのでしょうか。
選ばれる=最高品質だと仮定して、コンテンツを構成する本質的な要素と、それを実現するための具体的なポイントを掘り下げてみます。
テクニック論は「本質」ではない
web業界ではLLMO対策として、「こうすればAIに評価される」と、いくつかテクニックが語られています。
例えば、
- 知りたいことがすぐに分かる結論重視の構成
- 「もう他に調べる必要がない」と思わせる徹底した情報網羅
- 常に「最新」で「正確」な情報の提供
- 「なぜそう言えるのか」が明確な情報の裏付け
- スッと頭に入る「優しい文章」
- 文章だけではなくイメージを可視化した表現
- 疑問に先回りする気配り回答
これらは確かに、今のところ有効な手段であることは間違いありませんが、これを目的にしてしまうと、大きな落とし穴にはまってしまう…。
なぜなら、今重要視されているテクニックは、AIの進化速度を考えると、「今」だけ有効なものである可能性が高いからです。
AIがさらに賢くなれば、わざわざ結論を先に出さずとも、文章全体から重要な結論を自動で導き出して勝手に表示してくれます。
網羅的であることの意味も、AI自身が膨大な情報をまとめてくれるようになれば、その基準は変わってくるかもしれません。
つまり、これらの表面的な最適化は、AIの進化によってAI側で自動的に処理できるようになり、コンテンツを作る側が意識して行う意味が薄れていくことになるのです。
本当に大切なのは、テクニックを意識することではなく、ユーザー起点で考えること。
ユーザーの課題解決と満足度を最大化する「本質」を追求した結果として、上記のテクニックが自然と備わっている状態が理想だと言えます。
「最高品質」のコンテンツを構成する揺るぎない要素とは
ユーザー起点で考えた時、LLM時代に選ばれるコンテンツが持つべき最高品質とは具体的にどのような要素で成り立っているのか。
それは、AIの進化がどれだけ進んでも変わらない、コンテンツの「魂」と呼べる部分。
絶対的な「信頼性」と「専門性」
執筆者の透明性
「誰が書いたのか」は非常に重要です。
記事の執筆者が、その分野の専門家であること、豊富な経験を持っていること、そして信頼できる人物であることを明確に示しましょう。
単なる肩書きだけでなく、具体的な実績や、そのテーマに関する深い知見が伝わるようにプロフィールを明記。
AIも情報の出どころが信頼できるかを判断しますから、ここはとても大切な部分です。
深い専門知識
表面的な情報だけでは、AIもユーザーも満足しません。
そのテーマについて、基礎知識から応用、最新動向、そして「なぜそうなのか」「どうしてそういう結論になるのか」と根本的な理由まで、徹底的に深く掘り下げて解説。
専門用語を使う場合は、必ず分かりやすい言葉で丁寧に説明を加える配慮も忘れずに。
信頼の担保
提供する情報、特に数字などを出す場合は、必ず具体的な根拠を示しましょう。
データはどこから来たのか、検証・研究結果は誰が発表したものなのか、専門家の発言であればその専門家は誰なのか。
論文とまでは言わないものの、情報の裏付けを明確にすることで、読者やAIが「この情報は信頼できる」と確信できる状態にします。
また、あなたしか提供できない独自の調査結果やデータを盛り込むことは、信頼性を飛躍的に高める武器になります。
圧倒的な「独自性」と「希少性」
経験・思考・試行に裏打ちされた唯一無二の深い考え方
AIは、インターネット上の既存情報を学習し、組み合わせることで回答を生成します。
しかし、あなたやあなたの会社、現場の社員だけが持つ「生きた経験」、そこから生まれた「深い思考」、そして実際に「試して得られた結果」は、AIには決して生成できません。(仮にこのような回答をAIが生成した場合は、自身が体験していないため嘘にもなる)
自分たちしか持っていない一次情報や独自の視点こそが、コンテンツの「圧倒的な独自性」と「希少性」を生み出します。
競合には真似できない具体的な事例や知見
実際に自社が解決した顧客の課題、製品開発の裏話、現場での試行錯誤のプロセス、そこから得られた独自のノウハウなど、具体的な事例を盛り込みましょう。
これは、その分野の専門家であることの何よりの証明であり、他社が簡単に真似できない強みになります。
最高の「伝わりやすさ」と「行動促進」
読者の疑問を完全に解決する網羅性
ユーザーがそのテーマについて検索したとき、自社のコンテンツを読めば「もう他に調べる必要がない」と感じるほどの網羅性を目指します。
ユーザーが次にどんな疑問を持つかを予測し、先回りして関連するあらゆる質問に答えるコンテンツ設計を心がけましょう。
ただし、1記事に全ての情報は詰め込めないので、何記事か分割して、構造的に分かりやすくすることも大切です。
論理的で分かりやすい構成と表現
どんなに深い内容でも、伝わらなければ意味がありません。
最も重要な情報を早めに提示し、その後で詳細な説明に入る(ユーザーの時間を奪わない配慮)。
または適切な見出し(Hタグ)を使い、読者が記事全体の流れを把握しやすいようにしつつ、箇条書き・表・グラフ・図解などを効果的に使い、複雑な内容も視覚的に分かりやすくする。
もし専門用語を入れるのなら、必ずその場で簡単な言葉で解説を加える。
まるで会話をするように、ユーザーだからこそ読める、親しみやすい言葉遣いを心がけ、読者に語りかけるような文章で飽きさせない工夫も重要です。
ユーザーの行動や心理を一歩も二歩も先に進める価値
単なる情報提供で終わらせず、その情報を得たユーザーが「次はどうすればいいのか」「何から始めればいいのか」を明確に提示。
ユーザーの課題を具体的に解決するための実践的なアドバイスや、具体的な手順を示すことで、「これならできる!」と納得感と行動できる状態を目指します。
コンテンツは一冊の書籍を届けるような覚悟で
高品質なコンテンツの要素を突き詰めていくと、結果的に1記事へ投じる情報量は増え、労力もかかります。
しかし、それが圧倒的な品質を生み出すための道であり、単なるweb記事の文字数制限に囚われず、そのテーマにおける完全版・決定版、つまり一冊の書籍を作るような一球入魂の覚悟を持ってコンテンツ制作に臨むことが大切です。(この思考になれているかが重要)
LLM時代における企業に問われた覚悟
LLM時代に企業が生き残るためには、コンテンツに対する「覚悟」が、これまでの比ではないほど強く求められています。
コンテンツへの覚悟が企業の未来を左右する
もはやコンテンツは、作ればアクセスが増えるといった単純なマーケティングツールではありません。
企業のブランドそのものを構築し、未来の顧客との関係性を築くため戦略的に投資する資産になり得ます。
この資産に、どれだけ真剣に、そして長期的に投資する覚悟があるかが、企業の存続と成長を決める時代へ突入しています。
LLM時代における内製化の重要性
過剰な表現かもしれませんが、最高のコンテンツは、やはり自社の「中の人」でしか生み出せないと思っています。
それだけ社内で、熱量をもって取り組めるかが大事。
コンテンツの「魂」は自社で生み出したい
最も重要な「何を伝えるか」「なぜそれが言えるのか」と、コンテンツの核となる情報・専門性・独自性は、外部の誰にも真似できない、自社で今まで培われてきた経験や想いならではのものです。
社員や特に現場の担当者が持つ深い経験・知識、そして毎日の業務で汗水たらして行ってきた「思考」と「試行」が、コンテンツの魂(核)となります。
ここに、最大限のリソースと覚悟を集中させることが重要です。
自社独自の目線が「模倣」を生み優位性を高める
圧倒的な品質のコンテンツを自社独自の目線で生み出せば、その情報は業界の当たり前(スタンダード)となり、知識のない他社はそれを真似しようとします。
しかし、真似する側はそもそもの「経験」や「思考プロセス」がないため、真似はできても凌駕はできません。
この模倣される現象が、結果的に自社のコンテンツを最初の情報元(一次情報)として高評価を受け、その優位性が複利効果のように爆上がりしていきます。
スキルと経験の社内蓄積
コンテンツ制作を内製化することで、社員は市場のニーズを直接肌で感じ、コンテンツ制作のスキルを向上させ、成功・失敗から学び続けることができます。
この経験の蓄積が、さらに次の高品質コンテンツを生み出す基盤となります。
外部活用の新しい形と注意点
内製化が重要とはいえ、全ての企業がコンテンツ制作の全てを完璧に内製できるわけではありません。
だからこそ、外部委託のあり方も大きく変わります。
従来の丸投げ発注は「停滞を招く投資」
外部ライターやAIにテーマだけ与えて丸投げしてしまうと、ライターもAIも前提の知識がないため、基本的にはインターネット上の既存情報を頼りにするしかありません。
その結果、どこかで見たような、誰にも選ばれない低品質コンテンツが量産され、費用と時間だけが無駄になります。
さらに、コンテンツ制作に対するスキルや知識が社内になければ、提出されたものを「良い」と判断してしまう危険性もあります。
外部に依頼する場合の「軸」の重要性
外部に依頼するなら、コンテンツの骨子、核となるメッセージ、盛り込むべき独自データや事例といった「大筋の構成」は、なるべく自社で作成しましょう。
こうすれば、外部のライターは単なる情報収集者ではなく、あなたが狙った通りの「軸」に沿って情報をまとめる役割に徹することができます。
監修・編集の徹底
外部から上がってきた原稿は、必ず自社の専門家が「監修」し、コンテンツとしての品質を最終的に「編集」する体制を確立しておきましょう。
情報の正確性、専門性の深さ、独自性の有無、読者への分かりやすさなどを厳しくチェックします。
最適なハイブリッド戦略
LLM時代における最適な戦略は、コンテンツの魂(核となる情報と専門性)を自社で生み出す創造の内製化と、そのコンテンツを効率的に活用するための戦略立案・運用・分析・技術を外部の専門家と連携するハイブリッド型です。
「量」より「質と影響力」の時代に変化
従来のコンテンツマーケティングでは、予算を投じて広告枠を買い、大量の露出で顧客を呼び込む「札束で殴り合う」ような戦いがありました。
しかし、LLM時代は、この戦い方が通用しなくなります。
広告効果の低下
たとえばリスティング広告の場合、GoogleのAI概要が広告枠の上へ表示されるため、広告をクリックしてもらえる機会は減少することで、広告に頼り切るモデルが限界を迎えています。
「お金」ではなく「知識と信頼」の戦いへ
これからは、どれだけ顧客のニーズを深く理解し、それに応える質の高い情報を創造できるか、そしてそれを通じてどれだけ信頼を築けるか、知識と信頼の戦いになります。
LLMO対策のその先へ:見込み顧客の獲得とブランド形成
LLMO対策として最高のコンテンツを作り、見つけてもらうことに成功したとしても、それは集客の始まりに過ぎません。
最終目的である「顧客を増やすこと」を達成するためには、その先の戦略が不可欠です。
「見つけてもらう」は目的達成の入り口に過ぎない
AIが瞬時に回答を返してくれる時代では、ユーザーは自社のコンテンツを「最初から一語一句読み込む」モチベーションをほとんど持ちません。
AI概要で疑問が解決すれば、それ以上は深掘りしない人も多いと考えられます。
しかし、もし自社のコンテンツにたどり着いたユーザーがいるとしたら、それはAIが提供できる一般的な情報では解決できない「より深い課題」や「具体的なニーズ」を持った、非常に質の高い見込み顧客である可能性が高い。
その方々は、本当の意味での解決策や信頼できる情報源を求めています。
「少ないアクセス」から「高い顧客転換率」への戦略
アクセス数が少なくても、自社のコンテンツにたどり着いた貴重な見込み顧客を、いかに高い確率で顧客へと転換させるかが重要です。
目標は、「100人中1人がお客様になる」状態から、「10人中1人がお客様になる」ような高い転換率を目指すこと。
そのため、コンテンツを通じて関係性をどう深められるかを考え、具体的な導線設計も必要です。
価値ある「次の一歩」の提示
コンテンツの最後に、読者が「もっと知りたい」「この企業と関わりたい」と思えるような、さらに価値の高い情報や機会を明確に提示しましょう。
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 無料の専門資料 | ホワイトペーパー、eBook、事例集など、メールアドレスと引き換えにダウンロードできる、より深い情報。 |
| ウェビナー・セミナーの案内 | 自社の専門家が直接解説するオンライン/オフラインのイベント。 |
| 個別相談・デモの機会 | ユーザーの具体的な課題に対して、自社のサービスがどのように解決できるかを示す個別相談や製品デモンストレーション。 |
| 無料トライアル・診断ツール | 自社のソリューションを体験してもらうための入り口。 |
| 明確なCTA(Call To Action) | 「詳しくはこちら」「無料ダウンロード」「今すぐ相談する」など、読者が次に何をすればいいか、分かりやすく魅力的な言葉で示すボタンやリンクを効果的に配置します。 |
| リード育成(ナーチャリング)の仕組み | 獲得したメールアドレスなどのリード情報に対し、その後も定期的に有益な情報(メールマガジン、個別メール)を提供し続け、顧客の購買意欲を段階的に高める仕組みを構築します。 |
コンテンツが創る「未来のブランド」
LLM時代において、コンテンツは単なる集客ツールではなく、企業の「ブランド」そのものを構築する核となります。
企業としての専門性・信頼性の確立
質の高いコンテンツを継続的に発信することで、「この分野なら、この企業に聞けば間違いない」揺るぎない専門性と信頼感を市場で確立します。
顧客との深い共感
自社のコンテンツが、顧客の課題に深く寄り添い、真の解決策を提供することで、単なる情報提供者ではなく、「私たちのことを分かってくれる」共感と信頼を生み出します。
「相談先」としての地位確立
ユーザーが具体的な行動(製品購入、契約、問い合わせ)を起こす際に、AIの回答ではなく、「この企業に相談したい」「この企業から買いたい」の選択肢へつながるようにしていきます。
LLM時代は「本物」だけが生き残り未来を創る
これまで解説した内容は、かなり理想論に近いお話ではありますが、最初から基準を高めておかないと、実際に出てくるアウトプットが引き上がりません。
そしてLLMO対策は、AI時代のSEOの新しい形を表しますが、その本質は表面的なテクニックやバズワードに飛びつくことではありません。
企業が「本物」として、顧客にどれだけの価値と信頼を提供できるか「覚悟」そのものになる。
目先の安さや効率に囚われ、質の低いコンテンツへ無駄な投資をするのは、もはや企業の停滞を招く行為となるため、今こそ変わらない価値(顧客への真摯な姿勢、圧倒的な品質、揺るぎないブランド)を追求し、コンテンツをストック資産として積み上げていく覚悟を持つべき時だと感じています。
成長を続ける企業は、質の高いコンテンツを核とし、それを通じて顧客との深い関係性を築き、ブランドを確立する、本質的な戦略へ舵を切っています。
ぜひ、この記事の内容を参考に、本当の意味でのLLMO対策が進めば幸いです。