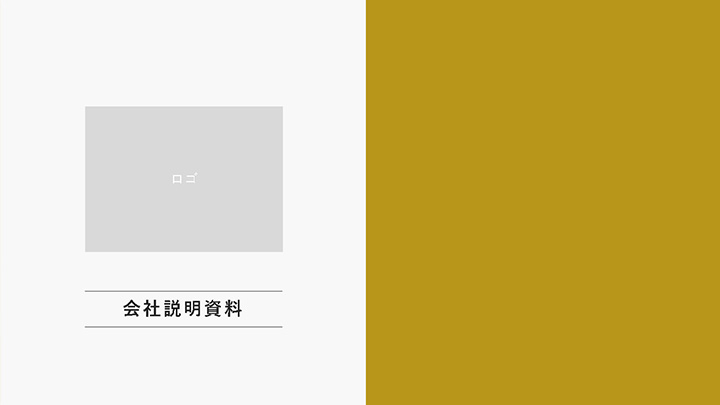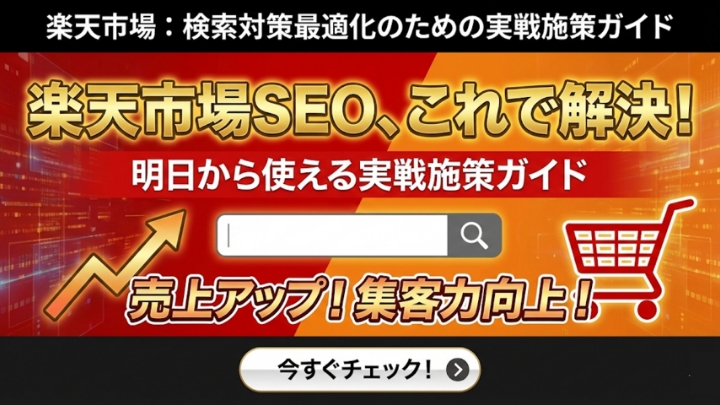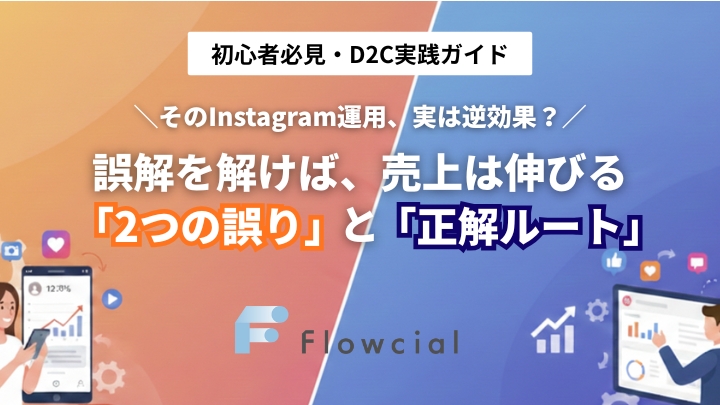いつも見て頂きありがとうございます!「エンプレス」の編集部:sugiyamaです。製造業系の企業さんが、新しいお客様を見つけるための、はじめの一歩となるマーケティング手法についてまとめています。
「技術力に自信はある。でもなぜか新規顧客が増えない…」
日本のモノづくりを支える製造業で働かれているあなたは、こんな不安を感じているかもしれませんね。
良いものさえ作っていれば…
いつか誰かに見つけてもらえるはず…
今は耐え忍ぶ時だ…
その信念のもと、製品の品質や技術を磨き続けてきたにもかかわらず、新規顧客が増えないと、成長が止まっているように感じてしまうことも。
長年お付き合いのある既存顧客からの安定した売上はありがたいものですが、それだけに頼っていると、もし取引が打ち切られたり、コストの安い海外製品に顧客が流れてしまった場合、それが大きなリスクにもなります。
この記事では、そんな状況を打破したいと考える、製造業の経営者や担当者であるあなたに向けたものです。
あなたが感じている不安、実はマーケティングによって解決できる角度は高いのですが、「マーケティング」と聞くと、なんだか難しそう、自社には関係ない、と感じるかもしれません。
しかし、マーケティングを「売れる仕組み作り」や「伝える力」などに変換した場合は、より身近に感じませんか?
製造業で見込み顧客(新規開拓)を獲得するには、自社の「技術を伝える力」を磨くことが大切なので、この記事で具体的な方法を、一つひとつ丁寧に解説していきます。
なぜ製造業では見込み顧客の獲得が重要課題なのか
「大口顧客がいるから、営業やマーケティングなんて必要ないよね。」
たしかに今安定しているなら、そう思われたことがあったと思いますし、現状維持の考え方は当然出てきます。
しかし、状況や世界情勢などが変わったらどうでしょうか?
例として、2025年に第47代アメリカ合衆国大統領へ就任したトランプ氏は、各国に関税をしかけてきました。
これにより、製造業は重い関税を強いられ、変革を余儀なくされています。
- 他社への乗り換えを考える
- 顧客がコスト改善を目指すため値下げを要求
- 自社で製造しようとする
など、現状維持は難しく、どの製造企業も変わらなければ、自社の売上・利益を圧迫するだけなので、考え方・体制・サプライチェーンの見直しが強制的に入り今のままではいられません。
だからこそ、有事の際にも対応できるよう、常に見込み顧客の獲得をし続けておく仕組み(※ 総じてマーケティング)が大切なのです。
「見込み顧客の獲得」は単なる営業活動ではない
見込み顧客を獲得することは「営業マンやマーケターがすること」だと、限定的な活動で考えられているなら、そこは改める必要があるかもしれません。
見込み顧客の獲得とは、
- 外部依存から脱却して主導権を取り戻すことである
- 価格ではない価値で勝負する土台を築くことである
この考え方を持てると、未来の成長を自分たちでコントロールできるようになるため、突発的に何か変革が起きても、お客様維持・獲得には困らなくなります。
すごく大事なことなので、それぞれを詳しく解説していきます。
「外部依存から脱却して主導権を取り戻す」とは?
多くの製造業が、下記のような顧客獲得経路を使っています。
・特定の元請け企業からの受注
・知り合いからの紹介
・展示会
・業界誌やweb媒体など外部の集客チャネル
…etc
これらのチャネルに頼っていますが、実はとてもリスクのある状態だとも言える。
たとえば、もしあなたの主要な取引先が、よりコストの安いサプライヤーを国内外で見つけ、取引を打ち切ったとしたらどうなるでしょうか?
あるいは、頼りにしていた展示会が開催されなくなったら?
このような外部の状況に自社の命運を委ねている状態は、いつ予期せぬリスクに見舞われるか分かりません。
自社で安定して見込み顧客を獲得する仕組みを築いておけば、外部の状況に左右されることなく、自分たちのタイミングで事業を動かせるようになる。
これは、「守り」から「攻め」へ、ビジネスの主導権を自社の手に取り戻すことにつながります。
「価格ではない価値で勝負する土台を築く」とは?
コストの安さを強みとする海外の製造企業が増える中、価格競争に陥ることは、ほとんどの場合、あなたの会社にとって得策ではありませんよね。
そこで重要になるのが、「価格ではない価値」で選ばれる企業になること。
あなたの会社が持つ独自の技術力、高品質な製品、長年の経験から生まれるノウハウ。
これらをきちんと「伝える」ことができれば、顧客は製品そのものだけでなく、「あなたの会社だからこそ解決できる課題」に価値を見出してもらえるようになります。
その価値が顧客の中で積み重なれば、「この課題なら、あの会社に相談しよう」と第一想起を勝ち取ることができます。
第一想起とは、選択肢がある中でも1番先に思い出される存在となったこと。
これが、永続的な競争優位性をもたらす「ブランド力」につながり、お客様に困らない成長を続ける企業へと変わるキッカケになります。
製造業が見込み顧客の獲得で陥りがちな負のループとは
多くの製造業が見込み顧客の獲得において、無意識のうちに悪循環へ陥っている可能性があるのも、その根本的な原因に、伝えることの苦手意識が存在するからです。
たとえば『職人さんや会社の技術は一級品ですが、あまりモノを語らない。』こんなイメージは昔のものかもしれませんが、普段から魅力や強みを、言葉として言語化するスキルを高めていないと、やはり伝わらない情報が多くある。
それゆえに、負のループへ陥りやすくなっています。
なぜ「伝える」技術が、見込み顧客の獲得障害になっているかと言えば、伝えられないものは存在しないのと同じだからです。
存在しない情報に、反応も興味も好感も持てません。
製造業が見込み顧客の獲得で陥りがちな負のループを断ち切るには「伝える」技術が必要なことを、もう少し具体的に解説していきます。
負のループ① 伝えることの壁がWebサイトを機能不全にする
あなたの会社もホームページを公開して、必要な情報を載せたり、お客様からの問い合わせを受けたりしていますよね。
しかし、会社概要や製品リストを載せているだけで満足していませんか?
もしそうなら、それは「名刺代わり」にしかなっておらず、顧客を獲得するツールとしては機能しておらず、ホームページ本来の役割がまっとうできていない。
それも、多くの製造業が「伝えること」に躊躇する理由として、二つの要因が存在しているからです。
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 職人気質 | 「良いものを作ればわかるだろう」の意識が情報発信の必要性を後回しにさせている |
| 技術流出への懸念 | 独自技術やノウハウを公開することで競合に真似されることを恐れている |
その結果、顧客が本当に知りたい情報(技術の詳しい解説、導入事例、価格の目安など)がWebサイトに不足し、オンラインからの集客が全くできないという状況が生まれます。
負のループ② すべての顧客は同じではない
ようやく見込み顧客を獲得しても、その後のアプローチを誤ると、せっかくのチャンスを逃してしまいます。
多くの製造業企業が、問い合わせてきた人、展示会で名刺交換した人、資料をダウンロードした人などを、すべて同じ見込み顧客として扱ってしまいがちですが、お客様それぞれの「状態」はまったく違ってきますよね。
| 層 | 状況 | 説明 |
|---|---|---|
| 明確層 | 今すぐ客 | 課題が明確で、すでに製品やサプライヤーを具体的に探している。 |
| 顕在層 | 比較検討客 | 課題は認識しているが、まだどの製品が良いか比較検討している。 |
| 準顕在層 | 情報収集客 | まだぼんやりと課題を感じており、解決策を探している段階。 |
| 潜在層 | まだ課題に気づいていない客 | まだ自社の課題にすら気づいていない。 |
これらの各層に、同じ営業トークや情報を提供しても、状況が違うのにうまくいくはずがありません。
たとえば、潜在層にいきなり「お見積もりはいかがですか?」と案内しても警戒されてしまい、関係はそこで途切れてしまう確率は高い。
すぐに電話の着信拒否、メールのブロック・迷惑メール設定により、せっかく労力をかけて獲得した見込み顧客が、一瞬のうちにいなくなってしまう。
すべての顧客は同じではないからこそ、それぞれの状況に合う表現や言語化が必要なので、伝えるスキルが求められます。
負のループ③ 組織内の課題と購買プロセスの複雑さ
製造業の購買プロセスは、複数の部署が関わるため、とても複雑で長期化しやすいですよね。
それは、技術部門・購買部門・品質管理部門・情報システム部門など、それぞれの担当者が異なる視点から製品やサービスを評価しているから。
顧客も、一つのサプライヤーに頼りすぎるリスクを避けるため、複数の会社と同時に、そして比較検討しながら進めるので、決定まで遅くなるのは当然かもしれません。
こうした複雑なプロセスを理解し、各担当者に響く情報を戦略的に提供していかなければ、苦労して獲得した見込み顧客も、最終的に他社へ取られてしまうリスクがある。
そのため、各プロセスごとで、適切に情報を「伝える」技術が必要となり、それによって決定までスムーズな進行が出来るようになります。
製造業の見込み顧客獲得におけるマーケティング戦略とは
製造業が見込み顧客を獲得するため、具体的にどのような対応をしていけばいいのか。
必要なマーケティングの流れを3つに絞って分かりやすく解説していきます。
ステップ1:Webサイトを生きた営業マンにする
Webサイトは、会社の顔であると同時に、24時間365日働く優秀な営業マンです。
しかし、多くの製造業のWebサイトは、その力を発揮できていない可能性もあるため、webサイトのパフォーマンスを最大化できるよう、以下2つのポイントが重要です。
① 意識改革:「技術公開」ではなく「価値を伝える」
ブログなどで情報提供はしたいものの、技術流出への懸念・不安があり、どうしても一歩踏み出せない…。
その気持ちはすごく分かります。(万が一、競合に真似されてしまったと考えると怖いですよね)
しかし、顧客が本当に知りたいのは、あなたの、そして会社の技術の全てではなく、知りたいのは「その技術が、自分の会社のどんな課題を、どのように解決してくれるか」。
これを伝えるためには、職人が持つ「暗黙知」を言語化することが重要ですが、そのまま専門用語を羅列したり、技術者だからこそ分かる表現をしても、伝わらないことがあります。
技術公開ではなく、どの技術がどのように顧客の悩みを解決するのか、相手に分かる表現が必要なので、意識改革と言語化のスキルはセットに考えましょう。
② 具体的なコンテンツのアイデア
専門的な知識を持つ技術者へ「いきなりブログを書いてください」と頼むのは、正直いって難易度が高いと思います。
技術や知識やノウハウに関しては右に出る人はいないけど、だからこそその複雑難解な情報を分かりやすく伝えるのは、相当のスキルが求められる。
そのため、作りやすい情報とはどんなものか、今すぐできるアイデアをまとめました。
事例の掲載
「A社が抱えていたコストの問題を、当社の独自の加工法で〇〇%削減できました」と具体的な事例は、顧客の心を最も動かします。
顧客の許可を得て、写真や体制図などを交えながら詳しく掲載しましょう。
事例といっても、導入事例・成功事例・失敗事例・他社事例など、実体験をもとにまとめられる情報は、今までの経験から言ってもたくさんあると思います。
ぜひ、それらの眠っていたお宝情報を伝えていくのがお勧めです。
FAQ(よくある質問)の充実
顧客からよく聞かれる質問や、問い合わせの多い内容を、Q&A形式でまとめます。
「なぜこの素材が最適なのか」
「他社の製品と何が違うのか」
など、顧客の疑問に答えるだけでも、大きな価値を提供できます。
たとえば、直接電話・メール・お問い合わせフォームで聞くのは心理的ハードルが高く、事前に質問・回答を載せておくと、顧客自身で解決できるようになるので、次のアクションにも進みやすくなり、見込み顧客の獲得にもつながります。
技術解説記事
専門用語を分かりやすく解説したり、製品の裏側にある工夫やこだわりを紹介したりする記事は、あなたの会社の技術力と信頼性が効果的に伝わります。
しかし「誰へ向けて書くか」によっても方向性が大きく違ってきます。
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 専門家相手 | 難しい専門用語も交えながら具体的に詳しく執筆 |
| 初心者相手 | かなり噛み砕いて初見でも分かるように執筆 |
技術解説では、単に技術を説明するだけでなく、自社に技術がお客様の課題にとって、どのように作用するのか分かりやすくまとめます。
ここが詳しく分かると、サプライヤー候補として考えてもらいやすくなるので、技術解説記事もお勧めです。
ステップ2:段階的なマーケティング施策で効果を最大化
今はまだWebからの集客がない前提だと、見込み顧客を獲得するマーケティングは、どのように進めればいいのか。
段階的に施策を進めることで、着実に成果が表れてくるため、流れをフェーズ1~3でまとめました。
フェーズ1:集客の土台作り
まずは、ターゲットとなる顧客に自社の存在を知ってもらうことが最優先です。
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 展示会・業界誌の活用 | 従来のオフライン施策を最大限に活かしましょう。単に名刺交換をするだけでなく、来場者の課題をヒアリングし、後日、個別に役立つ情報(Webサイトの記事など)を送ることで、オンラインへの接点を作ります。 |
| Web広告(集客の借り入れ) | 自社サイトの集客がまだ弱い段階では、業界専門メディアや技術系メディアへの広告出稿が効果的です。多くの人が集まる場所に広告を出すことで、あなたのWebサイトにターゲットを誘導する「集客の借り入れ」ができます。 |
フェーズ2:コンテンツ資産の構築
集客の土台が作れたら、今度は本格的に価値ある情報を提供できるwebサイト(営業マン)へと育てていきます。
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| ブログ・コラム | 顧客の課題解決に役立つノウハウ記事を継続的に発信します。これにより、検索エンジンからの流入を増やし、会社の資産となるコンテンツを蓄積できます。 |
| SEO | 検索エンジン(主にGoogle)にて検索結果の上位表示を目指すのが、SEO(サーチエンジン最適化)。検索エンジンにも人間(webサイトへ訪れる人)にも、情報が読み取りやすく、かつ有益な情報が多く含む記事を作り、オンライン上の集客を増やします。 |
| コンテンツマーケティング | コンテンツ(記事、動画など)により、webサイトへ訪れてくれた方の興味関心を引き付け、そして好感度や信頼を高めていき、最終的には自社が目的とするお問い合わせ・お申込みなどに繋げる流れを作ります。 |
| LLMO対策 | ChatGPTやGeminiなどの生成AIに参照されるように、有益で求められる情報をwebサイトへ掲載していきます。SEOとコンテンツマーケティングを行うことで、LLMO対策にもつながります。 |
フェーズ3:「引き合い」を効率的に増やす仕組み作り
「集客の土台とコンテンツ資産によってアクセスが増えた。」
これは嬉しいことですが、ただアクセスを増やすだけでは不十分です。
アクセスしてくれる方も今すぐ困っている方や、今後のための情報収集など、状況がグラデーションになっているので、その中から質の高い「引き合い」へとつなげる仕組みが必要になります。
その仕組み作りに必要なのが、以下の2つ。
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| ホワイトペーパーの作成 | 顧客の検討度合いが高いかを判断するため、詳細な技術資料や価格表、詳しい導入事例をまとめたホワイトペーパーを作成し、ダウンロードを促します。 |
| リードナーチャリング | 資料をダウンロードした顧客の行動履歴(Webサイトの閲覧ページなど)を分析し、関心度が高いと判断できたタイミングで営業がアプローチすることで、商談成立の確率を高めます。 |
ステップ3:最強の伝える体制を築く
「文章を書くのは苦手…」「そもそもリソースがない…」
無いスキルやノウハウを、今から現場の方に習得してもらうには、やはり時間がかかってしまいます。
そのため、将来的にはすべて自社完結できるようにしつつも、最短で進むに外部の力を借りることも視野に入れましょう。
「自社でやる」 vs 「外部に頼る」
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 自社でやる場合 | ノウハウが社内に蓄積され、コストも抑えられます。しかし、本業がおろそかになったり、専門知識がないために成果が出なかったりするリスクがあります。 |
| 外部に頼る場合 | 専門家のノウハウを活用することで、より早く成果を出すことができます。しかし、費用がかかることや、社内にノウハウが残りにくいというデメリットもあります。 |
時間をかけられればいいですが、それまで待てない・待ってもらえない場合は、やはり外部の専門家の力を借りた方が、戦略立案・企画・制作・実施・改善までの一連の流れも速くなる。
お金はかかりますが、その分、本来かかるであろう時間の短縮にも繋がるので、外注は選択肢としてもっておくのがお勧めです。
最適なのは「ハイブリッド型」
最も効果的なのは、自社と外部が協力する体制です。
技術者が「素材」(メモ、写真、口頭での説明など)を提供し、外部のプロがそれを「料理」(顧客が求める分かりやすい文章やデザイン)する。
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 自社 | 専門情報と技術は保有しているが具現化・可視化が苦手 |
| 外部 | 具現化・可視化は得意だが専門情報と技術はない |
お互いを補完し合うことで、自社に合う見込み顧客を獲得するマーケティングができるようになります。
生成AIはあくまでアシスタント
最近の生成AIは文章作成にとても便利ですが、安易に使うのは危険です。
とくに製造業であれば、専門性の高さから、生成AIでは適切な情報を作れない場合もあるのと、AIに自社のコアな技術情報を入力すると、学習されて情報が漏洩するリスクもあります。
たしかに生成AIへ任せれば、膨大な学習データの中から、最適だと思われる情報を返してくれるので、あたかも全て正解をくれていると感じやすいのですが、あくまで必要そうな情報の上澄みを組み合わせているだけ。
AIが生成する文章は「平均値」であり、あなたの会社独自の強みや情熱を伝えることはできません。
生成AIは、あくまで文章のたたき台を作ったり、表現を整えたりする「アシスタント」として活用し、最終的には「伝える」ことを得意とするプロの力を借りることが成功への近道です。
まとめ
製造業が見込み顧客を獲得する上で、「伝える」ことがあなたの会社の技術力と同じくらい…それ以上に重要なことになっている。
見込み顧客を獲得するマーケティング手法は色々ありますが、製造業においては自社の魅力を伝える技術も持つことで、競争優位性が獲得できます。
ぜひ、技術と同じくらい、伝えることも意識して、マーケティング活動を進めてみましょう。