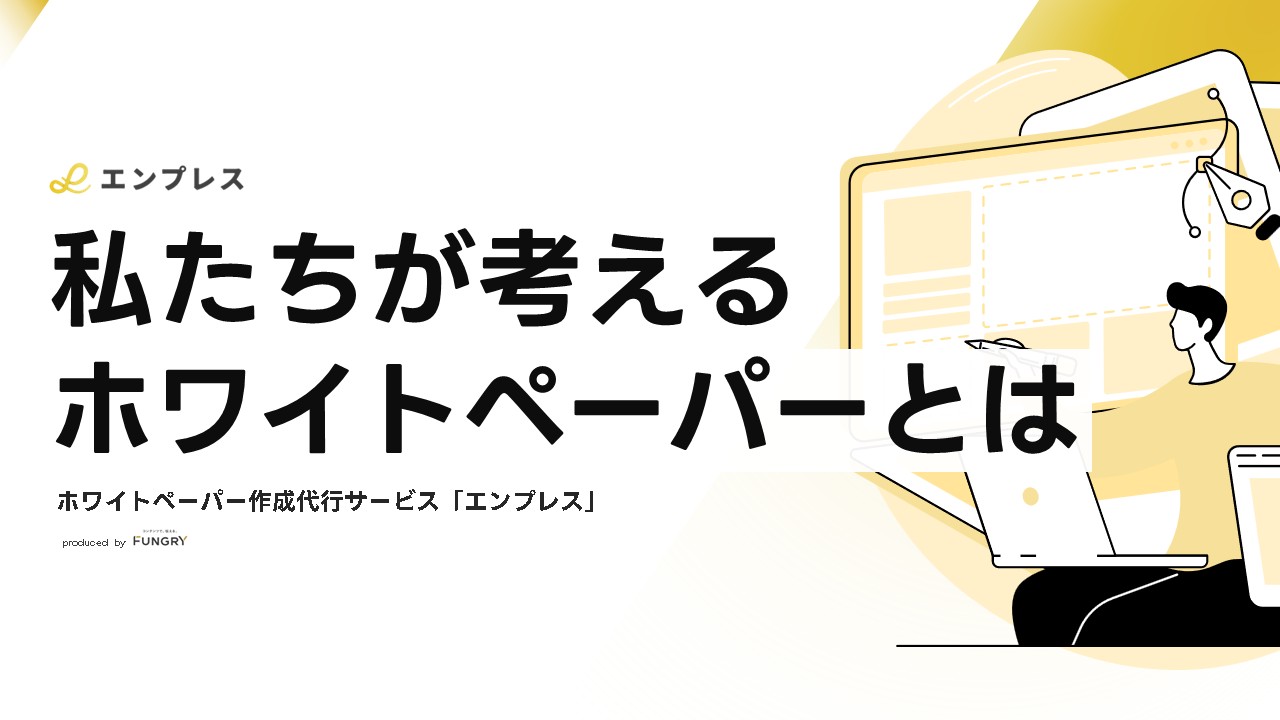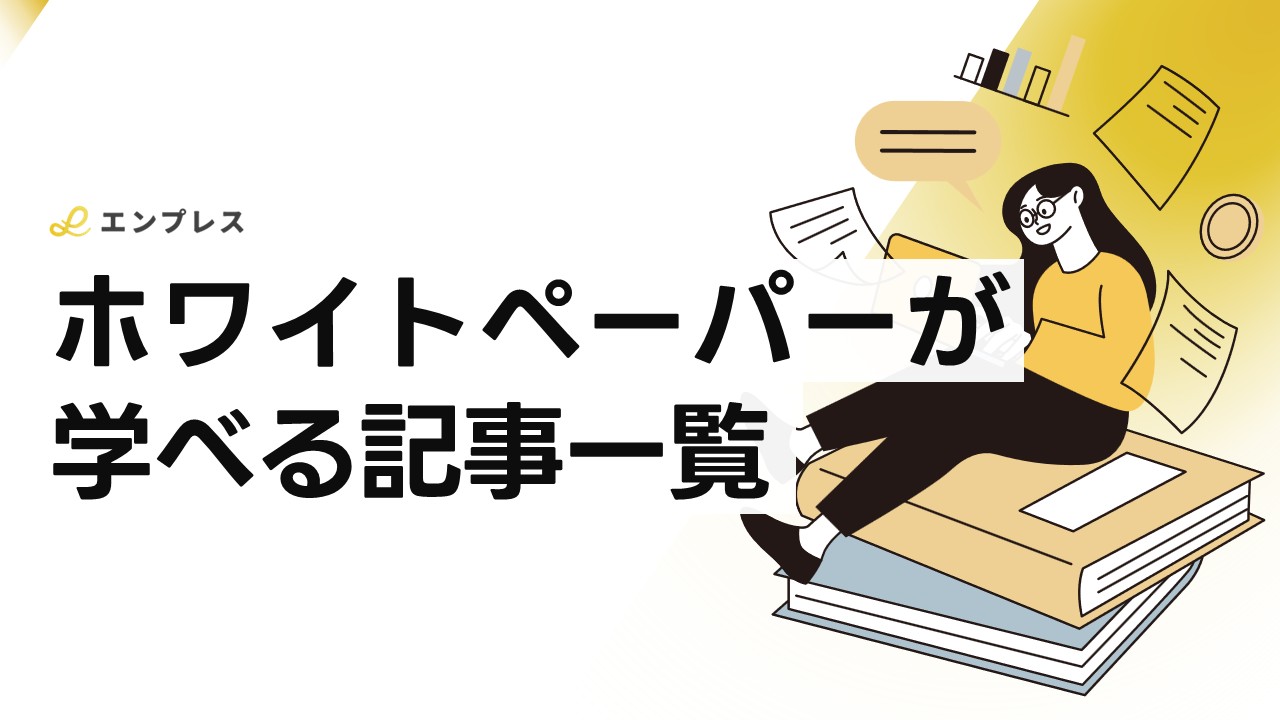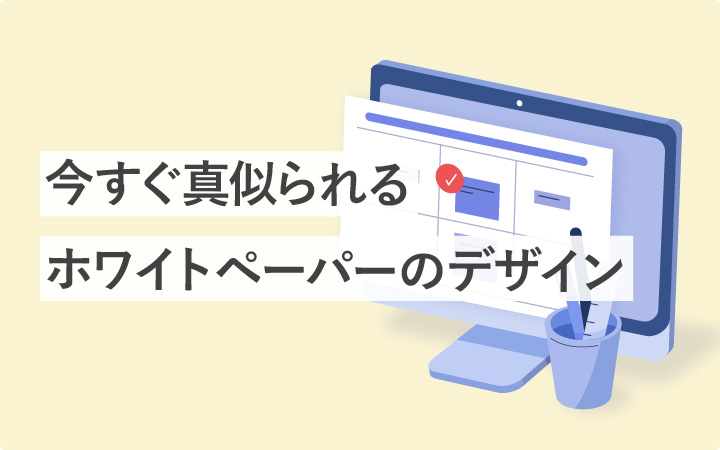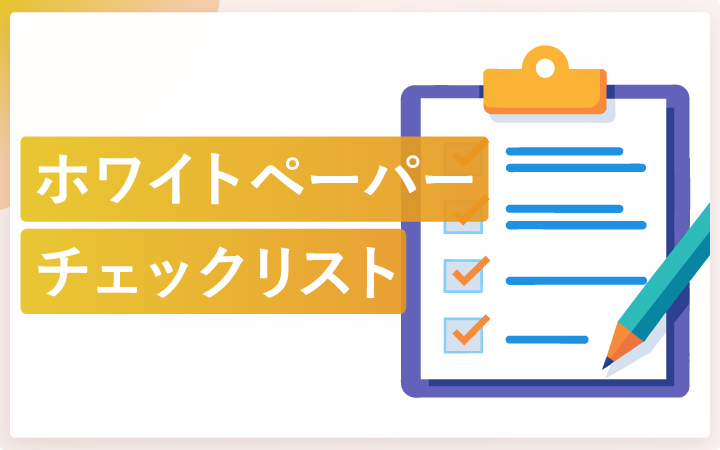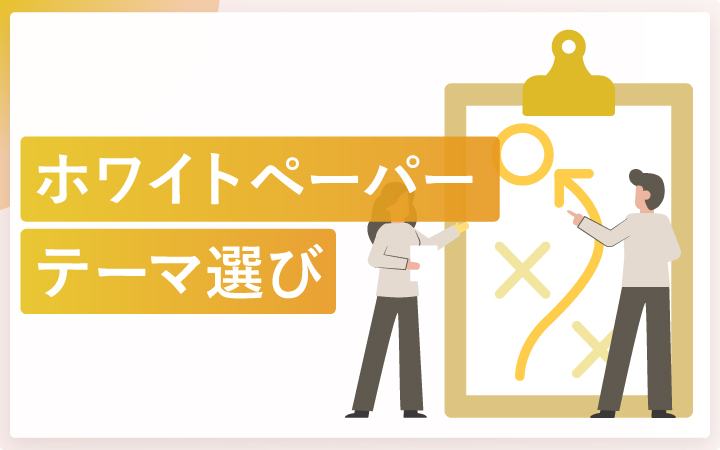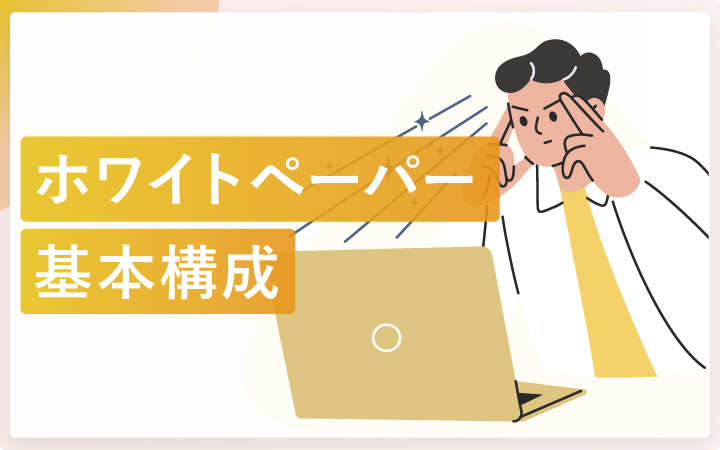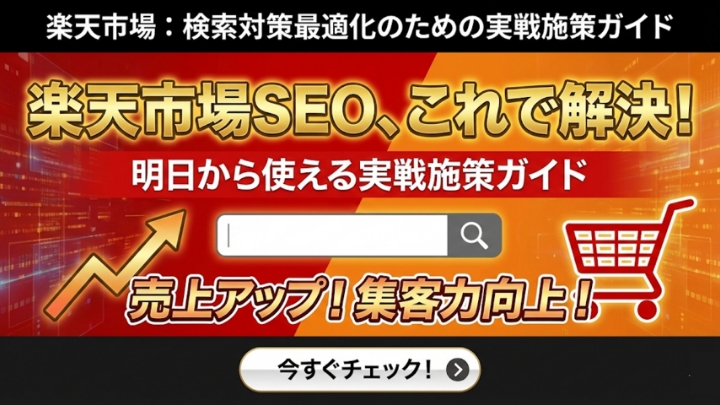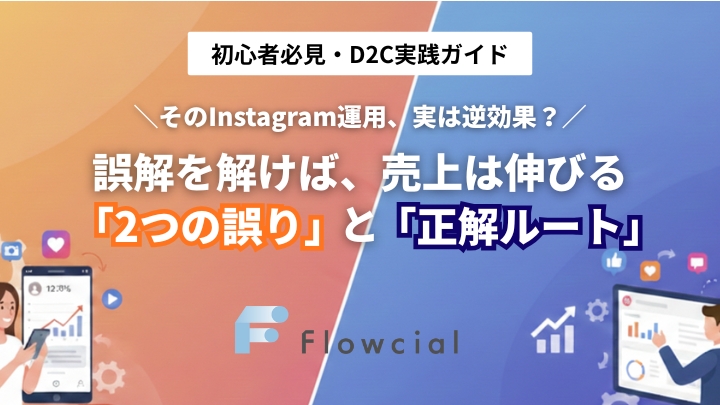いつも見て頂きありがとうございます!「エンプレス」の編集部:sugiyamaです。ホワイトペーパーは、今いる社内の人材だけで量産できます!
マーケティング活動をもっと活発にしたいと考えたとき、「ホワイトペーパー」の活用はとても有効な手段です。
見込み顧客の獲得(リード獲得)から、興味関心を引き上げる(ナーチャリング)まで、幅広いシーンで活躍してくれる。
しかし「ホワイトペーパーをたくさん作りたいけど、うちでは難しいかも…」と感じていませんか?
一つ作るにも、企画を考えたり、文章を書いたり、デザインしたりと、専門的なスキルやノウハウがたくさん必要ですよね。
「それならプロにお願いしよう!」と思っても、制作を外注すると費用がかさんでしまい、数を増やすのはなかなか大変です。
この「費用」と「手間」がネックになって、ホワイトペーパー作りがなかなか進まないと、よくお話も聞きますが、ホワイトペーパーは必ずしも外注しなくても作れますし、むしろ社内で作る(内製する)ことで、たくさんのメリットが生まれます。
ホワイトペーパー制作の内製が進められるよう、必要な情報をまとめたので参考になれば幸いです。
- 目次
- ホワイトペーパーの内製で得られるメリット
- ホワイトペーパー内製でつまずきやすいデザインの落とし穴
- ホワイトペーパーの活用目的によってデザインの考え方は変わる
- ホワイトペーパーを内製する6つの手順
- ホワイトペーパーを量産するためのコツ
- ホワイトペーパーの内製はマーケティング活動の未来を変える!
ホワイトペーパーの内製で得られるメリット
ホワイトペーパー制作を「外注」ではなく「内製」で進めていくのは手間もありますが、かなり大きなメリットがあります。
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| ① コミュニケーションがスムーズ | 外注先に指示を出す手間や、意図がうまく伝わらないといったすれ違いが減ります。 |
| ② ノウハウが社内に蓄積される | 作れば作るほど、自社の中にホワイトペーパー作りのコツや知識がたまっていきます。これは将来のマーケティング活動にとって大きな財産になります。 |
| ③ マーケティング活動の幅が広がる | 自分たちでサッと作れるようになれば、キャンペーンやセミナーに合わせて素早くホワイトペーパーを用意でき、より多くのチャンスを掴めるようになります。 |
「内製なんて本当にできるの?」そう思われたかもしれませんが、やれないことはない。
スキル・ノウハウがなくても、考え方やコツさえ分かれば、自社のメンバーだけで進めていけるので、必要な情報を確認していきましょう。
内製するデメリットとは?
ホワイトペーパーを内製する場合、どうしても自身の業務と兼業で進めなくてはいけない場合が多く、集中して時間が取りづらいかもしれません。チームメンバー全員がそのような状況にもなるので、プロジェクトの責任が分散して、結局は作れない…なんてことも。外注するメリットもあるので、制作パートナーの相談を検討されたい場合は、「ホワイトペーパーの外注先おすすめ」ページもご確認ください。
ホワイトペーパー内製でつまずきやすいデザインの落とし穴
ホワイトペーパーを内製で進めようとする時、必ずぶつかる壁があります。
それは「デザイン」です。
「プロが作ったみたいにかっこいいデザインじゃないとダメ?」
「デザイナーがいないから、うちでは無理だ…」
そう考えてしまう気持ちはよく分かります。
私たちもホワイトペーパー制作代行のご相談をよく頂きますが、お客様から「デザインにもこだわりたい」とご要望をいただくことがあります。
しかし、その時必ずお伝えしていることが「過剰なデザイン品質を求めない」こと。
このような発言をすると「え、デザインって重要じゃないの?」とお客様からも言われますし、あなたも疑問に思うかもしれませんね。
もちろん、デザインは大切ですが、それよりもホワイトペーパーを使う「目的」や「場面」によっては、必要以上に力を入れるべきではない理由がたくさんあるんです。
なぜホワイトペーパーのデザインに力を入れすぎちゃいけないの?
ホワイトペーパー制作時は、デザインに対する意識を変えなければいけません。
それは「デザイン」の定義が独り歩きして、収集が付かない状態に陥りやすく、過剰な対応をしてしまいがちになるから。
主な原因としては4つあり、
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| ① デザインは主観でブレやすい | 「もっとこうしたい」「ここが違う」など、デザインの良し悪しは人によって意見が分かれやすく、何度も修正を繰り返して、完成までに時間がかかってしまいがちで制作の遅れにもつながります。 |
| ② 情報を的確に提供できることが前提 | 企業イメージを高めるためのブランディングが目的なら別ですが、リード獲得や見込み顧客の育成(ナーチャリング)が目的のホワイトペーパーでは、見た目のかっこよさよりも「どんな情報が、どれだけ分かりやすく書かれているか」が圧倒的に重要なので、最低限読みやすいデザインであれば十分なんです。 |
| ③ 自己満足のデザインになりやすい | 「これくらいちゃんと作れば大丈夫だろう」と安心感を得るため、無意識のうちに情報量を増やしたり、インパクトを追求してしまうことがあります。しかし、お客様が本当に知りたいのは「課題を解決する情報」であって、デザインそのものにはあまり興味がありません。 |
| ④ 情報消費は一瞬 | お客様はホワイトペーパーを隅から隅までじっくり読むことはほとんどありません。ざっと目を通して、自分に必要な情報がどこにあるかを探します。せっかく時間をかけて凝ったデザインにしても、すぐに読み飛ばされてしまうので、かけた労力に見合う効果が得られにくい。 |
ピカピカでおしゃれな、見た目を極限まで高める「デザインを重要視」するフェーズは、もっと後の段階です。
リード獲得やナーチャリングなど、マーケティング活動の初期段階では、過剰なデザイン品質は必要なく、むしろデザインにこだわりすぎると制作が進まず、内製や量産が難しくなってしまいます。
マーケティング活動に使うホワイトペーパーでは、「デザインを最小限に抑えること」が成功のカギになることを、ぜひ覚えておいてください。
ホワイトペーパーの活用目的によってデザインの考え方は変わる
ホワイトペーパーを内製するなら、「どんな目的で使うホワイトペーパーなのか」によって、力の入れ具合を変えることがとても重要です。
大きく2つの考え方に分けてみましょう。
【初期】お客様との接点を増やし興味関心を引き付けるホワイトペーパー
マーケティングの初期段階で使うホワイトペーパーであり、例えばウェブサイトから資料をダウンロードしてもらうことで見込み顧客を獲得したり、メルマガで配信して、まだあまり興味がない見込み顧客に情報を提供して、少しずつ関係を深めたりする時に使います。
この段階では、お客様が「これ、私のことかも!」「この情報、知りたい!」と直感的に感じてもらうことが最も大切。
つまり、お客様の心の中にある「ぼんやりとした悩み」や「知りたいこと」と、ホワイトペーパーの「テーマ(内容)」がどれだけピッタリ合っているかが重要になります。
テーマが7割、デザインは3割くらいのイメージで、「読みやすさ」を意識したシンプルなデザインで十分です。
【後期】信頼性や権威性を高めブランド価値を積み重ねるホワイトペーパー
すでに接点のあるお客様や、商談・契約に進む可能性のあるお客様に対して使うホワイトペーパーであり、例えば具体的な解決につながる提案資料や、詳細な調査レポート、導入事例集などがこれにあたります。
この段階では、お客様はすでにあなたの会社やサービスに興味を持って頂いており、だからこそ、より深い信頼感や安心感を与えるため、見た目の美しさや分かりやすさも重要になってきます。
テーマが3割、デザインが7割くらいのイメージで、会社のブランドイメージに合った、質の高いデザインを追求する段階です。※ テーマを蔑ろにしていいわけではなくすでにお客様の解像度が高くそこにかける時間は減らせるためデザインに時間を回すという意味
もし、リード獲得やナーチャリングの段階で「デザインがかっこいいから」と見た目の理由だけでダウンロードしてくれた人がいたとしても、それは「デザイン」に興味があるだけで、あなたの会社のサービスや課題解決には興味がない可能性はとても高い。
ターゲットとズレてしまい、その後の商談にはつながりにくく、時間だけが過ぎてしまうことになります。
このように、ホワイトペーパーを活用したい「フェーズ(段階)」によって、必要な品質・力の入れ方は大きく変わるので、この違いを理解せずに、最初からどんなホワイトペーパーもデザインに凝ろうとすると、内製化は失敗に終わってしまう可能性が高くなります。
ホワイトペーパーを内製する6つの手順
実際にホワイトペーパーを内製していくための具体的な手順を見ていきましょう。
STEP1 思考の切り替え(マインドセット)
まず何よりも大切なのが、あなたやチームメンバーの「考え方(マインドセット)」を切り替えること。
「ホワイトペーパーはプロが作るもの」
「デザインが良くないとダメ」
このような固定観念は一度捨てて、まずはシンプルに作ってみたり、お客様が求めているのは情報である意識を強めて、ホワイトペーパーに対する認識を切り替えることがスタートです。
この思考の切り替えが、内製化成功の第一歩になります。
STEP2 自社の状況把握
次に、自社の状況をしっかりと把握しましょう。
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 誰がどのくらいの時間をホワイトペーパー制作に使えるか? | 担当者の選定や、週にどれくらいの時間を充てられるかを確認します。 |
| どんな情報があるか? | 既存のブログ記事、営業資料、社内資料、お客様への提案書など、ホワイトペーパーのネタになりそうな「情報資産」を洗い出します。すでに持っている情報から作ると、時間と手間を大幅に削減できます。 |
| 内製化の目標は? | 「月に〇本作成する」「リード獲得数を〇〇%増やす」など、具体的な目標を設定しましょう。 |
STEP3 顧客の情報把握
ホワイトペーパーは、お客様の課題を解決することが基本の情報媒体です。
だからこそ「お客様がどんな悩みを持っているのか?」を徹底的に知ることが重要です。
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 顧客の声を聞く | 営業担当者から、お客様がよく口にする悩みや質問を聞き出します。 |
| ウェブサイトのアクセス解析 | どんな記事がよく読まれているか、どんなキーワードで検索してくるかを分析します。 |
| 競合他社の情報 | 競合他社がどのようなホワイトペーパーを出しているか、参考にしてみるのもOK。 |
お客様の「無意識の課題」まで掘り下げていくことで、本当に響くホワイトペーパーのテーマが見つかります。
STEP4 企画・構成・台割・ライティング(言語化)
ここから具体的な制作に入ります。
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 企画 | 誰に(ターゲット)、何を(テーマ)、どう伝えたいのか(目的)を明確にします。 |
| 構成 | ホワイトペーパーの目次や流れを決めます。お客様がスムーズに読み進められるよう、論理的な流れを意識しましょう。 |
| 台割(ページ割り) | 各章でどのくらいの情報を、何ページで表現するかを大まかに決めれば、全体のボリューム感を把握しやすくなります。 |
| ライティング(言語化) | 決めた構成と台割に沿って、実際に文章を書いていきます。専門用語は使わず、誰が読んでも理解できる平易な言葉で説明することを心がけてください。 |
「難しい言葉を使わない」「箇条書きを活用する」「具体例を入れる」を基本にすれば、読者の理解を深めることができます。
STEP5 デザイン(具現化)
文章が固まったら、いよいよデザインです。
繰り返しになりますが、リード獲得やナーチャリングが目的のホワイトペーパーでは、最低限の読みやすさと視覚的な整理整頓があれば十分です。
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| フォーマットの統一 | 毎回ゼロからデザインするのではなく、あらかじめ「テンプレート(ひな形)」を作っておくと効率的です。ロゴの配置、文字のフォントやサイズ、色の使い方など、シンプルなルールを決めておきましょう。 |
| 図やグラフの活用 | 文字ばかりだと読みにくいので、必要に応じて図やグラフ、アイコンなどを効果的に使って、視覚的に分かりやすく表現しましょう。 |
| ツール選び | PowerPointやGoogleスライドでも十分に作成可能です。最近では、Canva(キャンバ)のような無料で使えるデザインツールも増えており、非デザイナーでもプロ並みの資料が簡単に作れます。 |
もし社内にデザイナーがいなくても、PowerPointのような描画ツールを使えば、十分なクオリティのホワイトペーパーが作れますので、「見た目のデザイン」よりも「中身」が重要であることを忘れずに、制作を進めましょう。
STEP6 ブラッシュアップ
完成したホワイトペーパーは、一度で完璧にしようとせず、必ず「ブラッシュアップ(改善)」を行いましょう。
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 客観的な視点 | 社内の複数人で目を通し、「分かりにくいところはないか?」「誤字脱字はないか?」などをチェックします。 |
| 公開後の効果測定 | 公開後は、ダウンロード数や読了率、その後の見込み顧客の動き(問い合わせにつながったかなど)を分析します。 |
| 改善点の洗い出し | 分析結果をもとに、「タイトルを変えてみよう」「内容の一部を修正してみよう」など、改善できる点を見つけて、次のホワイトペーパー制作に活かしましょう。 |
ホワイトペーパーは作って終わりではありません。
公開後も効果測定と改善を続けることで、より効果的なツールへと進化していきます。
ホワイトペーパーを量産するためのコツ
「よし、内製にチャレンジしてみよう!」と思っても、次に「何本くらい作ればいいの?」と疑問が出てくるかもしれませんね。
具体的な目標本数は、マーケティング戦略・状況・目的によって様々ですが、例えば「月間100件の新しい見込み顧客を獲得したい」と考えた場合、ホワイトペーパーが1本しかないと、多くの人にダウンロードしてもらうのはかなり難しいことが想像できますよね。
自社のオウンドメディア経由でリード獲得する場合、アクセス数の多い記事がいくつかあれば可能ではありますが、競合も増えている中で、一本足打法はとてもリスクの高い施策になってしまいます。
そこで、様々なテーマのホワイトペーパーが10本くらいあれば、より多くの見込み顧客にアプローチでき、リード獲得の可能性も高まります。
究極的な話をするなら、集客ができているウェブサイトの記事一つひとつに対して、関連するホワイトペーパーを一つずつ用意する考え方が理想的です。(すごく大変ですが…)
お客様は自分が知りたい情報をピンポイントに知りたいので、全般的に好まれる情報ではなく、記事の内容に合わせたホワイトペーパーを用意することで、ダウンロードしてもらえる確率が格段に上がります。
例
× テーマAの記事に対してテーマB+のホワイトペーパー
〇 テーマAの記事に対してテーマA+のホワイトペーパー
そう考えると、ある程度の数のホワイトペーパーが必要になるため、「量産体制」を整えることがとても重要に。
量産を可能にする3つのポイント
ただ数をこなすだけでなく、以下のポイントに注意することで、効率的に高品質なホワイトペーパーを量産できるようになります。
シンプルにする(チーム内で定義を揃える)
「シンプルに作ろう」と言っても、人によって「シンプル」の定義はバラバラ。
「Aの要素とBの要素は必ず入れる」「文字数は〇文字以内」「デザインの飾りは最低限にする」など、チーム内で具体的なルールを決めておくことが重要です。
これにより、担当者が変わっても品質がブレず、スムーズに制作を進められ、コミュニケーションロスや認識ズレから起きる、デザイン軸のブレを無くすことができます。
デザインルールを定めたフォーマットを用意する
誰が作っても同じ品質になるよう、ホワイトペーパーの「ひな形(フォーマット)」を準備しましょう。
フォントの種類やサイズ、見出しの付け方、図やグラフの配置場所、色の使い方などをあらかじめ決めておくことで、判断基準ができデザインに迷う時間がなくなり、効率的に作業を進められます。
企画構成の「型」を複数用意する
毎回ゼロから企画を考えるのは大変です。
そのため「課題解決型」「事例紹介型」「ノウハウ提供型」など、いくつかのシナリオパターン(型)を用意しておくと便利。
新しいホワイトペーパーを作る際に、これらの型に当てはめる形で内容を肉付けしていくことで、企画にかかる時間を大幅に短縮でき量産しやすくなります。
ホワイトペーパーの内製はマーケティング活動の未来を変える!
マーケティングは、今すぐお客様になってくれる方から、将来的に顧客になる可能性のある方まで、さまざまな見込み顧客と接点を持ち、関係性を深めていく活動です。
その中で、ホワイトペーパーは計り知れないほどの可能性を秘めています。
- デマンドジェネレーション(見込み顧客の獲得・育成・選別)の入口として
- ウェブサイトの記事を深掘りした資料として
- セミナーやウェビナーの内容をまとめた資料として
- 動画コンテンツのテキスト版資料として
など、活用できるシーンは多岐にわたります。
また、ノウハウ集、調査レポート、成功事例、製品・サービス紹介など、ホワイトペーパーの種類も実にたくさんあり、マーケティング活動のあらゆる場面で活用でき、その品質と活用方法によって、成果が大きく変わってくる奥深さも持っています。
ホワイトペーパーを内製できるようになるだけで、可能性の幅は格段に広がる。
最初は少し難しく感じるかもしれませんが、ご紹介した手順とコツを参考に、制作と量産をぜひチャレンジしてみてください。
もし、デザインフォーマットの作成や、プロのアドバイスを受けながら制作を進めたい場合は、いつでもお気軽にご相談ください。